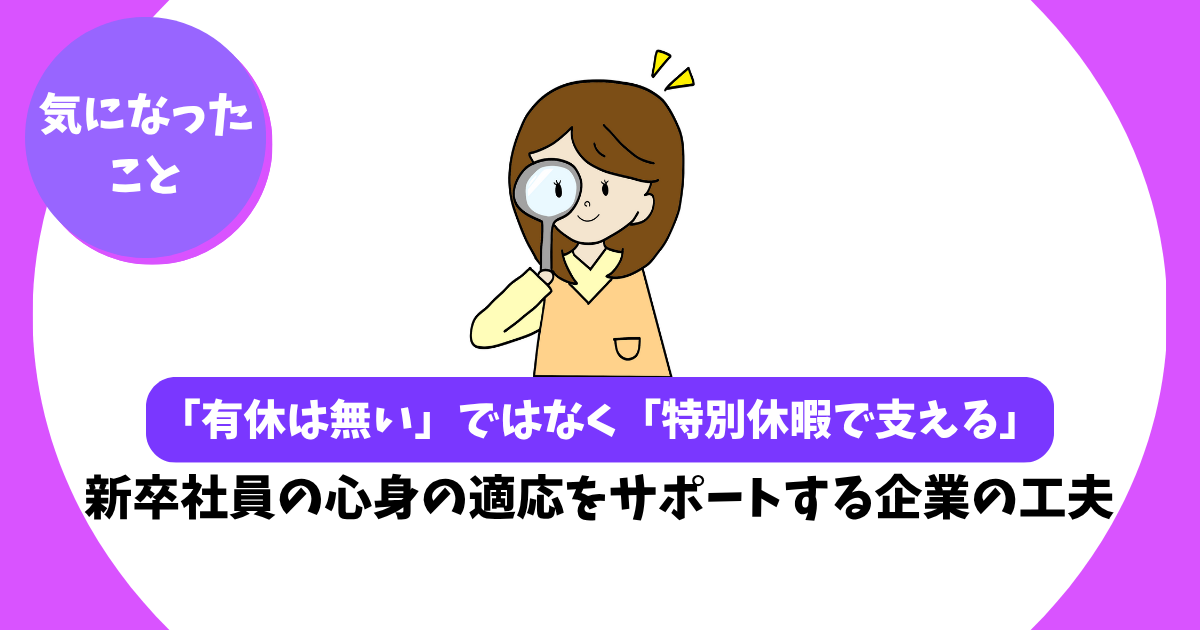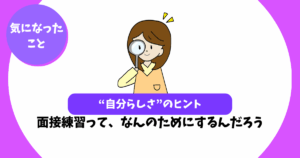“静岡で自分らしく働く”を本気で考えるなら。

- 新卒社員の離職率を下げたいと考えている中小企業の経営者
- 入社初期の新人教育や定着施策を検討している人事担当者
- 新卒採用後のフォロー体制を強化したい採用責任者
- 社員のモチベーション維持・エンゲージメント向上に課題を感じている人事・労務担当者
- 福利厚生や特別休暇制度の導入・改善を検討している経営層
- 自社の魅力を採用広報や企業PRで高めたい広報担当者
- 労働基準法や有給休暇制度の運用について正しく理解し、実務に活かしたい管理職
- 新入社員の心理的安全性を確保するための環境整備を進めたい組織づくりの責任者
はじめに
新卒社員にとって、入社してから最初の6か月間は仕事を覚えるだけでなく、人間関係や職場文化に慣れる大切な時期です。
しかし、この期間は年次有給休暇がまだ発生せず、体調不良や家庭の事情があっても休みづらい状況に置かれることがあります。
そこで企業側から「欠勤」ではなく、もっと前向きに使える特別休暇を用意することで、新人が安心して働き始められる環境を整えられるのではないでしょうか。
本記事では、労働基準法の正しい理解とともに、「新卒特別休暇」や「ウェルカム休暇」など、企業独自の制度として導入できる取り組みのヒントをご紹介します。
新入社員が感じる“はじめての正社員”の壁
中小企業の現場で新卒社員からよく聞かれるのが、「毎日8時間働くことにまだ慣れない」「最初の1か月(または半年)がとても長く感じた」といった声です。
これは決して怠慢ではなく、学生生活から社会人としての生活への急激な切り替えに起因する、自然な反応です。
特に正社員として初めて会社に所属し、責任を伴う環境に身を置くことは、大きな緊張を伴います。
ハラスメントや過重労働がなくても、日々の業務や職場の空気に慣れるまでには、個人差があります。
「半年間は有休がない」という制度の正しい理解
労働基準法では、正社員に年次有給休暇が発生するのは原則として「継続勤務6か月かつ8割以上の出勤」が要件です。つまり、入社から半年間は原則として法定の有休は発生しません。
企業によっては入社日から有給が付与されることもありますが、そうでない場合この期間に欠勤する場合は、給与控除や欠勤扱いとなることが一般的であり雇用契約の本質としても当然のことです。
また有給が付与される企業であっても、入社すぐには中々「慣れない環境で疲れた」という理由では“休めない雰囲気”という職場の空気も感じ、まじめな気質の新入社員は有給を申し出ることは控えてしまうでしょう。
“静岡で自分らしく働く”を本気で考えるなら。

欠勤を推奨しない―企業としての対応のあり方
当然ながら、企業として「欠勤しても構わない」「体調不良でも無理しなくていい」とだけ伝えるのは適切ではありません。
欠勤は雇用契約上の労務提供義務を果たせなかった結果として記録されるものであり、それを推奨することは制度上も実務上も望ましくありません。
そこで、企業としては「欠勤」ではなく、制度として新入社員を支える方法を取り入れたらいかがでしょうか?
「ウェルカム休暇」や「新卒特別休暇」の導入を
当社では、顧問企業の新卒社員からのヒアリング結果をもとに、以下のようなアドバイスをしています。
「入社から半年間の心理的・身体的な適応期間において、年次有休がないことで生じる不安を解消するために、企業独自の“新卒特別休暇”を設けてはどうか」
この特別休暇は、以下のような形での導入が効果的です。
- 入社日から取得可能(試用期間中も可、新入社員一斉など)
- 年間1~3日の範囲で付与
- 病欠や通院、家庭事情など柔軟に取得可能
- 上司の承認制とし、業務に支障がないよう調整可
特別休暇が生む「安心して働ける職場」
社内制度によって「休むことができる」という安心感は、新入社員の定着とモチベーション維持に大きく寄与します。特別休暇は、取得率の低い有休を補完するだけでなく、企業の「人を大切にする姿勢」を可視化する手段にもなります。
“静岡で自分らしく働く”を本気で考えるなら。

最後に
「有休がない=休めない」という不安を防ぐには、企業側が適切な制度を用意し、正しい情報提供を行うことが不可欠です。
新卒社員が安心して社会人生活に適応できるよう、制度面・心理面の両面からのサポートを整えることは、小規模の企業であっても効果的なPRとなり、将来的な戦力確保につながります。
公式ラインで無料相談受付中