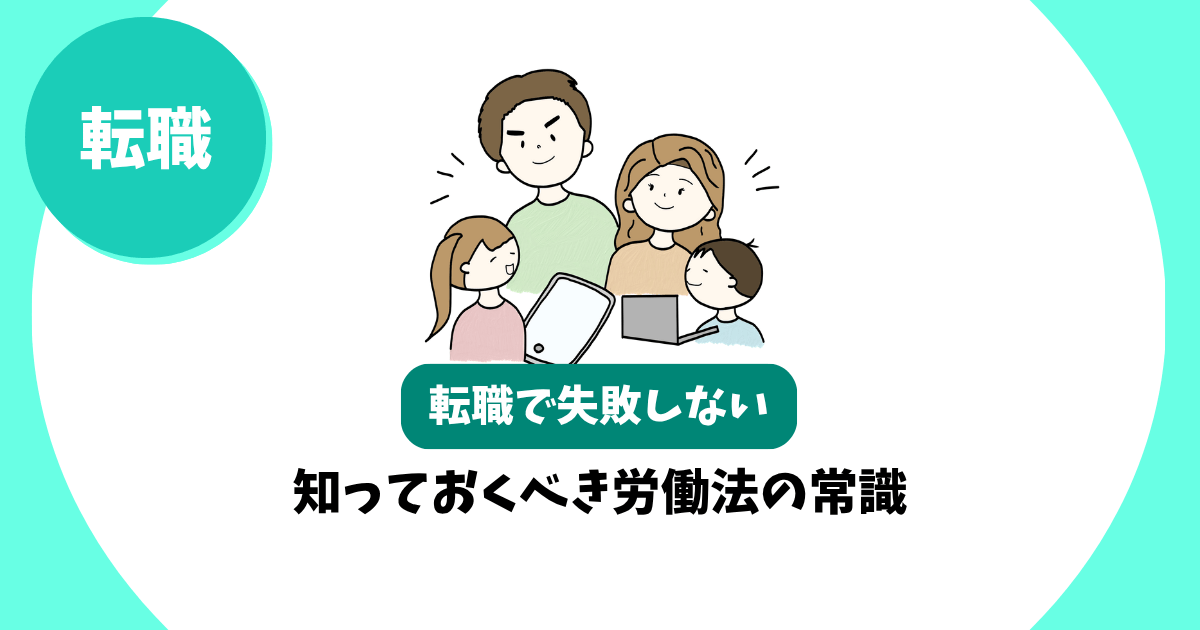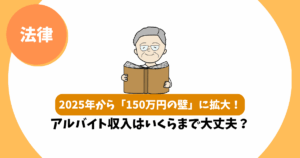“静岡で自分らしく働く”を本気で考えるなら。

- 転職を考えているが、法律上の手続きやルールに不安がある方
- 退職の申し出や有給休暇の消化など、実務的な対応に迷っている方
- 内定取消や未払い残業代など、トラブルが起きたときの対処法を知っておきたい方
- 前職の情報の取り扱いや契約上の注意点を理解しておきたい方
- 法律の専門家ではないが、正確な基礎知識を身につけて転職をスムーズに進めたい方
はじめに
新しいキャリアを目指して転職をするとき、「退職の手続きは?」「有給休暇は本当に消化できる?」「内定取消はありえる?」といった法律的な疑問や不安がつきものです。
曖昧な理解のまま進めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれたり、本来受け取れるはずの権利を放棄してしまったりするリスクがあります。
この記事は、転職を検討している一般の社会人の方々に向けて、労働基準法や労働契約法などの根拠に基づき、退職や権利に関する重要なルールを平易に解説します。
この記事を読めば、退職や内定取消に関する法律的なルールを正しく理解でき、現在の職場との円満な関係を保ちつつ、自信を持って次のキャリアへスムーズに移行するための具体的な知識が得られます。
転職活動を安心して進めるためにも、ぜひ最後までお読みください。
転職時の「退職」に関する法律と注意点
退職の申し出はいつまでに?(労働契約の原則と解雇制限)
転職を決意し、現在の会社に退職を伝える際、「いつまでに言えばいいのか」は大きな疑問点です。
期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、法的な原則は民法で定められていますが、職場のルールを無視することは、円満な退職を妨げる可能性があります。
労働契約は、労働者と使用者が対等な立場で合意に基づいて締結し、変更されるべきものです(労働契約法 第3条第1項)。
双方は、信義に従い誠実に、権利を行使し、義務を履行しなければなりません(労働契約法 第3条第4項)。就業規則に退職の申し出期間が定められている場合、円滑な業務引継ぎのためにも、それに従うことが社会人としての誠実な対応と言えます。
一方で、労働者が不当に解雇されないよう、労働基準法では厳しい解雇制限が設けられています。
例えば、労働者が業務上の負傷や疾病のために療養のために休業する期間、または産前産後休業の期間、およびその後30日間は、使用者は労働者を解雇することができません(労働基準法 第19条)。
これは、労働者の生活と安全を守るための重要な法律上の原則です。
労働者には退職の自由がありますが、会社都合の解雇には厳格な法律上のルールがあることを理解しておきましょう。
内定が取り消されたら?(内定取消のルール)
転職活動を経て無事に採用内定を得た後に、企業側の一方的な都合で内定取消が行われると、労働者は大きな不利益を被ります。
内定は、一般的に「始期付解約権留保付の労働契約」と解釈され、法的にはすでに労働契約が成立している状態にあります。企業がこれを一方的に解消することは「解雇」に準ずる行為とみなされます。
法律上、労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使にあたっては、それを濫用してはならないとされています(労働契約法 第3条第5項)。
したがって、企業が内定取消を行うためには、客観的に合理的な理由が必要とされ、その合理性がない場合は権利濫用として無効となる可能性が高いです。
特に、学校を卒業する予定の者(新規学卒者)について、企業が採用内定を取り消したり、撤回したりする際は、公共職業安定所等(ハローワークなど)にその旨を通知しなければならないと定められています(職業安定法関連規則)。これは、新規学卒者の雇用の状況を適切に把握し、必要な指導を行うための法律上のルールです。
もし不当な内定取消に遭遇した場合は、迅速に公共職業安定所などに相談してください。
知っておきたい「お金と時間」の法律知識
未消化の有給休暇はどうなる?
転職前に、使い残した年次有給休暇(年休)の消化は、労働者に認められた法律上の権利です。
継続して勤務し、所定の要件を満たしていれば、労働者は年次有給休暇を取得できます(労働基準法 第39条の規定に基づく権利)。
年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために与えられます。
労働者が退職したからといって、すでに発生している年休の請求権が変更されることはありません(労働基準法 第83条は災害補償を受ける権利について変更されないことを示しています)。
実務上の注意点として、有給休暇は「労働者が請求する時季に与えなければならない」とされていますが、企業側には「事業の正常な運営を妨げる場合」に時季を変更する権利(時季変更権)があります。
しかし、退職が間近に迫っている場合、企業が時季変更権を行使しても、退職日を超えての変更は事実上不可能であるため、退職前の年休消化は認められるのが一般的です。
ただし、年休の権利には消滅時効があります。時効期間については本ソース群に具体的な記載はありませんが、付加金の請求権については違反のあった時から五年以内に行使しなければならないと定められています(労働基準法 第114条ただし書き)。
年休の時効も延長されているため、取得を希望する場合は計画的に申請しましょう。
未払いの残業代は請求できる?
日々の業務で法定労働時間を超過して働いたにもかかわらず、適正な割増賃金(残業代)が支払われていない場合、転職を機に未払い分を請求することは、法律によって認められた権利です。
労働基準法は、労働者の労働時間を原則として休憩時間を除き一週間に40時間、一日について8時間を超えて労働させてはならないと定めています(労働基準法 第32条)。
これを超える時間外労働や休日労働、深夜業に対しては、企業は割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法 第37条の例による)。
もし企業がこの割増賃金の支払い義務に違反していた場合、労働者は裁判所に訴えることで、未払い金と同額の付加金の支払いを命じてもらうことが可能です(労働基準法 第114条)。
この付加金支払いの請求権は、違反のあった時から五年以内に行使しなければなりません。
実務上の注意点として、未払い残業代を請求する際は、ご自身の労働時間を証明するための客観的な証拠(タイムカードの記録、業務指示のメール、出退勤記録など)を確保することが非常に重要です。
また、企業が設けた減給の制裁規定があったとしても、その金額には上限(一回の額が平均賃金の一日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1)が設けられています(労働基準法 第91条)。
転職で守るべき「情報」と「契約」のルール
前職の情報を持ち出していい?(個人情報の取り扱い)
転職後、新しい職場で前職のノウハウや顧客情報を使いたいと考える方もいるかもしれません。
しかし、前職の機密情報や顧客情報を持ち出す行為は、重大な法律違反となる可能性があります。
企業は、取り扱う個人情報について、その漏洩や不正利用の防止に努める義務があります(個人情報保護法)。
個人情報とは、例えばDNAの塩基配列や、顔の骨格や容貌を電子計算機に供するために変換した符号など、特定の個人を識別できる情報を含みます(個人情報保護法関連政令 第1条)。
また、企業が労働者を採用する際、求職者の従事すべき業務の内容、賃金、労働時間、社会保険の適用などに関する事項を明確に示さなければなりませんが(職業安定法関連規則 第5条の3)、前職で取得した顧客情報を転職先の利益のために利用することは、前職との労働契約上の守秘義務(信義誠実の原則:労働契約法 第3条第4項)に反する行為となり得ます。
実務上の注意点として、前職の業務で得た情報は、機密情報や個人情報に関わらず、一切私的に利用したり持ち出したりしないことが、後の法律的なリスクを避けるために最も重要です。
まとめ
転職を成功させるためには、キャリア戦略だけでなく、法律的なルールと自分の権利を正しく理解しておくことが重要です。
退職ルールの理解、未払い残業代や有給休暇の適切な請求(付加金の請求は違反から5年以内)、そして予期せぬ内定取消 法律リスクの把握は、安心して次のキャリアへ踏み出す土台となります。
特に、労働契約の原則(労働契約法 第3条)や、採用時の労働条件明示(職業安定法関連規則 第5条の3)など、関係法律の知識を持つことで、不当な扱いや誤解を避け、交渉を有利に進めることができます。
もし、転職プロセスにおいて具体的な法律上の問題や権利の侵害に直面した場合は、この記事で得た知識を基に、適切な行政機関(公共職業安定所、労働基準監督署など)や専門家(弁護士など)へ相談する一歩を踏み出してください。
本記事における法律の解説は、あくまで一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する専門家の法律相談に代わるものではありません。
“静岡で自分らしく働く”を本気で考えるなら。

よくある質問
- 転職活動中であることを会社に言わずに進めても問題ないですか?
-
期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は職業選択の自由があり、通常、就業時間外の転職活動は私的な行為として自由に進めることができます。
会社に報告する法律上の義務はありません。
ただし、労働契約上の信義誠実の原則(労働契約法 第3条第4項)に基づき、業務に支障をきたさないよう配慮が必要です。 - 採用面接で聞かれても答える必要がない個人情報はありますか?
-
公共職業安定所は、すべての利用者に対し、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地(家柄)などを理由として差別的な取扱いをしてはならないとされています(職業安定法 第3条)。
これは求人者にも求められる姿勢です。
求職者側は、これらの差別につながりかねない質問や、家族の状況など、業務遂行に直接関係のない個人情報について、答える義務はありません。 - 労働条件が、求人情報と違っていた場合、内定辞退できますか?
-
求人者が求職者に対し、従事すべき業務の内容、賃金、労働時間などの労働条件を明示することは法律上の義務です(職業安定法関連規則 第5条の3)。
もし明示された労働条件が事実と異なっていた場合、内定辞退が認められる可能性は高いです。
また、明示された労働条件が就業規則で定める基準に達しない場合、その部分の労働契約は無効となり、就業規則の基準が適用されます(労働契約法 第12条)。
公式ラインで無料相談受付中